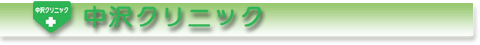 |

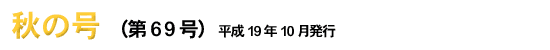
解説シリーズ[心を考える](その6); ア ル コ ー ル 依 存 症:(前) アルコール依存症、ちょっと堅いことばですが、以前は「アルコール中毒」(アル中)と呼ばれていました。ここでいうアルコールとは、もちろん「お酒」のことです。酒は、コーヒーやタバコと同じように嗜好品と呼ばれます。しかし、酒は他の嗜好品と違った面をもち、他の嗜好品と同様には扱えません。酒にはいろいろな顔があり、多様な姿があり、簡単にはとらえられないものです。ハレの日(結婚式やお祭りなど)やお祝いの席で乾杯し、ケの日(葬式や法事など)では献杯し、宴会・パーティー・儀式には欠かせないものです。一日の仕事を終えての帰り道、同僚たちと居酒屋で一杯やりながらの「飲みニケーション」、または自宅での夕食時、晩酌で一杯、これらを不思議な光景とは誰も思いません。つまり、社会生活の中で必要なものであり、ある人は酒をこよなく愛し、また、ある人は酒を心から憎む、ということもあるのです。最近あらゆる場面で嫌われているタバコとは、明らかに扱いが違います。 大変むずかしい課題ではありますが、今回、酒と人との関係、特に「アルコール依存症」として問題となる状況について解説してみたいと思います。 <酒、その不思議で難解なもの!> 酒は、生活に潤いをもたらす、ストレスを解消する、人間関係をスムーズにする、というように、さまざまなプラスのイメージがあります。しかしその裏には、「酒害」と呼ばれるたくさんの暗い事実が隠れています。アルコール依存症はその代表です。お酒をたくさん飲み続ければ、アルコール依存症になるのは当然のことです。なぜなら、医学的には、アルコールは麻薬や覚醒剤と同じドラッグ(薬物)の一種と考えられています。合法であろうと非合法であろうと、ドラッグは脳とからだを破壊していきます。アルコールというドラッグは、現代の日本でたまたま合法化されているにすぎません。 <なぜアルコール依存になるのか?> アルコール依存症とは、薬物依存症の一種で、飲酒などアルコールの摂取によって得られる精神的、肉体的な薬理作用に強く囚われ、自らの意思で飲酒行動をコントロールできなくなり、強迫的に飲酒行為を繰り返す精神疾患である、といわれます。 アルコール依存症は、すでに心理的、身体的依存に陥っている状態です。つまり、何をしてでもお酒を飲みたいという強烈な欲求と、お酒を断つと激しい禁断症状が出るような状態なのです。 具体的にいうと、飲酒パターンが病的なことが特徴です。宴会など機会がある時だけ飲む「機会飲酒」や、晩酌や寝酒など習慣的に飲酒する「習慣性飲酒」の場合は、飲む量が適量であれば正常な飲酒といえます。ところが、自分で自分の飲酒をコントロール出来なくなり、飲みだしたら止まらなくなったら病的な飲酒です。たとえ、1回に飲む量が少なくても、1日に一人で日常行動の合間に何回も飲むようになると、アルコール依存症と見なされます。更に、飲む量が増えて一人で飲んで寝て、起きてまた飲む「連続飲酒」は、アルコール依存症の終末状態といえます。 ドラッグであるアルコールは、いったん習慣性がつくと、なかなかやめることができません。これは、脳の中にドラッグを求める回路ができてしまうためです。この回路は人をあやつり、いかなる犠牲を払ってもドラッグを取らせるようにしむけます。アルコール依存症の人がお酒をやめられないのは、意志や道徳の問題ではなく、脳内にできたアルコール回路の作用によるのです。だからこそ、依存「症」という病名がついているのです。アルコール依存症は病気、それも進行性の病気です。医学的な治療が必要な病気だ、といえます。 <アルコール依存症になりやすい人とは?> アルコール依存症になりやすい「体質」があります。依存症になりやすいのは、 酒を飲んでも赤くならず二日酔いしにくい人(アルコールの処理能力が高い) 気持ちよい酔いが味わえる人(脳の「アルコールへの感受性」が高い) このような体質は遺伝するといわれており、家系内に「大酒飲み」と言われる人がいる場合は、飲酒の習慣をつけないことで依存症の予防をすべきです。 アルコールが肝臓で分解される過程でできる「悪酔い物質;アセトアルデヒド」は、これをさらに分解する酵素によって処理されます。「酒に強い」と言われる人は、この酵素の働きが良好で、アセトアルデヒドが血液中にふえませんので、悪酔いせず、飲んでも顔に出ないし乱れないのです。反対に「弱い」と言われる人は、酵素の働きが弱い、または全く働かない人です。 このように、酒に強く顔色が変わらない人は、たくさん飲んでも体調に異変がないため、気づかないうちに大量のアルコールを飲んでしまうことになり、かえって依存症になる危険性が大きいのです。 <アルコール依存症はどのように進行するか?> アルコール依存症の人も、何とかして適量のアルコールで済ませておこうとか、あるいは今日は飲まずにいようとか、考えていることが多いのです。しかし、自分で飲酒をコントロールできなくなると、過剰な飲酒を続けることによって、さまざまな問題を起こすことを知っているにもかかわらず、飲み始めると自分の意志では止まらなくなって酩酊するまで飲んでしまう。このような「強迫的飲酒」に進んでくると、常にアルコールに対する強い渇望感が生じ、酒に酔った状態・体内にアルコールがある状態にならないと気がすまなくなったり、調子が出ないと思うようになります。医師に止められていても、勤務中で酒を飲んではいけない時間であろうとずっと飲酒を続けるという「連続飲酒発作」がしばしば起こるようになります。さらに症状が進むと身体的限界が来るまで常に「連続飲酒」を続けるようになり、体がアルコールを受け付けなくなるとしばらく断酒し、回復するとまた連続飲酒を続けるという「山型飲酒サイクル」のパターンを繰り返していきます。ここまで症状が進むとかなりの重症です。 飲酒量が極端に増えると、やがて自分の体を壊したり(内臓疾患など)、社会的・経済的問題を引き起こしたり、家族とのトラブルを起こすようになったりします。それでさらにストレスを感じたり、ひどく後悔したりするものの、それを忘れようと、精神的苦痛を和らげようと、またさらに飲酒を繰り返します。 こうなると、飲酒を中断した際、様々な禁断症状が出ます。軽いものであれば、頭痛、不眠、イライラ感、発汗、手指や全身のふるえ、めまい、吐き気など。重度になってくると「誰かに狙われている」といった妄想や幻覚・幻聴を伴い、けいれん発作なども起こるようになります。本人にとってこれらは苦痛である為、それから逃れる為に、また飲酒をすることになります。 <たとえばこんなふうです> 65才の男性、自営業。2年前に、息子に事業を譲ってから酒量が増えました。もともとは清酒2合ぐらいの晩酌でしたが、日中も飲むようになり、酒量が増えて1日に5合を超えるようになりました。酒量を減らすように家族に注意されても守れず、夜は泥酔して眠り、夜中にトイレに行こうとして転んでケガをすることもありました。酒を飲む一方で、ちゃんとした食事をしなくなり、やせてきたため家族が心配して内科医にかかり、肝臓の障害を診断されました。病院に入院しましたが、入院2日目から手足や体の震えがひどくなり、「虫がみえる」などと言うようになり、精神科病棟に移りました。栄養補給をしながら、「禁断症状」に対処する治療を続け、なんとか快方に向かうことができました。 (以下、次号へ続きます) [酒にまつわることば・文学] 酒にまつわることばはいろいろありますが、少し拾ってみます。 [酒は百薬の長];酒にまつわることばで、まず浮かぶのはこのことばでしょう。適度の飲酒ならば、どんな薬よりも健康のためによい、と酒を賛美していうことばで、酒飲みが自己弁護のためによく使います。その出典は、中国の歴史書「漢書」で、前漢の皇帝が出した、塩・酒・鉄を専売とする法令の文章中に出てくることばです。酒百薬之長、嘉會之好(酒は多くの薬の中で最もすぐれており、めでたい会合でたしなむよきものである)、というものです。 [飲みニケーション];アルコールには食欲を増進させる作用と緊張を緩和させる作用があります。お酒を適量飲むことによって、心身ともにリラックスし、理性の働きが弱まることにより会話は弾み、コミュニケーションを円滑にすることができます。「胸襟を 開く薬を 酒という」という川柳があります。思わず、上司の悪口や愚痴が出たり、本音が出てしまったり−−−。「赤ちょうちん 串1本に ぐち10本」という川柳もあります。 古今東西、酒は文学者によって語られ、歌人によって詠まれています。 歌人・若山牧水(明治18年〜昭和3年)は、"酒仙の歌人"とも称され、旅と自然と酒をこよなく愛した漂泊の歌人です。 酒量たるや1日に1升以上を飲む大酒豪で牧水というより牧酔ですが、ついには肝臓を病み、43歳で世を去りました。親族は末期の水の代りに酒を以って唇を湿した、と伝えられています。生涯に残した七千首のうち酒を詠った歌が二百首以上にも及ぶといわれます。少し拾ってみますと、 *白玉の 歯にしみとほる秋の夜の 酒は静かに飲むべかりけり *人の世に たのしみ多し然れども 酒なしにしてなにのたのしみ *うまきもの 心にならべそれこれと くらべまわせど酒にしかめや *語らむに あまり久しく別れゐし 我等なりけりいざ酒酌まむ *それほどに うまきかとひとの問ひたらば 何と答へむこの酒の味 *酒のため われ若うして死にもせば 友よいかにかあはれならまし 吉田兼好(1283年?〜1353年?)は、「徒然草」第175段で、酒について「百薬の長とはいへど、万の病は酒よりこそ起これ。」と書いています。「酒は百薬の長」と言うけれど、多くの病気は、酒が原因である。といいながら、続く文章の中では、「かくうとましと思ふものなれど、おのづから、捨て難き折もあるべし」こんなふうに、酒はいけないものだと思うけれど、やっぱり捨ててしまうには惜しいものもある、と言っています。さらに、「近づかまほしき人の、上戸にて、ひしひしと馴れぬる、またうれし。さは言へど、上戸は、をかしく、罪許さるゝ者なり。」仲良くなりたい人が、酒好きで、魂まで通じるようになれたとしたら、うれしくなる、なんだかんだ言って、お酒を飲む人は、楽しいし、罪がない人である、と言っています。 貝原益軒(1630年〜1714年)は「養生訓」で飲酒の害と益について詳しく説いています。「酒は天の美禄なり。少しのめば陽気を助け、血気(ストレス)をやはらげ、食気(食欲)をめぐらし、愁いを去り、興を発して甚(はなはだ)人に益あり。多くのめば、又よく人を害する事、酒に過ぎたる物なし。ー中略ー 少しのみ少し酔へるは、酒の禍なく、酒中の趣(おもむき)を得て楽多し。人の病、酒によって得るもの多し。酒を多くのんで、飯をすくなく食ふ人は、命短し。かくのごとく多くのめば、天の美禄を以て、却て(かえって)身をほろぼす也。かなしむべし。 ー中略ー 酒を多く飲む人の、長命なるはまれなり。酒は半酔にのめば、長生の薬となる。」 十一世紀ペルシャの四行詩集「ルバイヤート」では、代表的詩人としてオマル・ハイヤームが有名です。ハイヤームも、酒についてたくさんの四行詩を書いています。二編の詩を取り上げてみます。 春が来て、冬がすぎては、いつの間にか 人生の絵巻はむなしくとじてしまった。 酒を飲み、悲しむな。悲しみは心の毒、 それを解く薬は酒と、古人も説いた。 いつまで一生をうぬぼれておれよう。 有る無しの論議になどふけっておれよう? 酒をのめ、こう悲しみの多い人生は 眠るか酔うかしてすごしたがよかろう! |
夏の号(第68号)へ ⇒新年号(第70号)へ